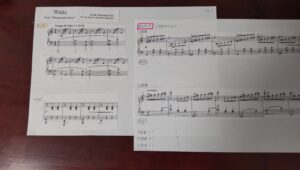この夏休みには表参道カワイで開催された
モスクワ音楽院のネルセシアン教授レッスンを聴講しました
理想的なレッスンとは…改めて考えさせられました。
レッスン曲は
ラヴェルの鏡やプロコフィエフのソナタなどのレッスンでした
ラヴェルでは
自分の感情を入れ込んで弾くのではなく
何かのイメージや映像を音で描写していく
フレーズごとにどんな映像が自分に浮かんでくるか考え表現していく
湿った音 乾いた音
指に電気が走ってるようにピリピリした音など
曲のキャラクターを考え
音色を選ぶ事が特に大事。
蛾の冒頭、速く弾きすぎると
細かい和声や音の動きに聴衆がついて
いけない
人に分からせる感じでゆっくり弾いた方が良いとのアドバイス✨
なるほど〜😯
綺麗なんだけどなんかよく分からない曲だな〜
やはり弾いた事ないと理解しづらいな🥲
正直思ったのだが、
多少ゆっくり弾いた演奏だと
音のきらめきや意外な音の組み合わせの妙が、感じられ親しみを感じました
道化師の朝の歌では
道化師の歴史、絵画
フラメンコとの関係
プロコフィエフでは演劇
また彼の他のオーケストラ作品との関連
バレエなど
いろんな事に造詣が深く
そんな話や
先生時々弾いてくれる演奏が
本当に素晴らしく✨✨✨✨
自然と
練習もしたくなる感じ。
こういうレッスンが理想的だなあと思いました
そのためには
自分のアンテナもいつでも広げておき
日々自分の練習もしないとなあとつくづく感じました(^_^;)